« 2013�N3�� |
Main
| 2013�N5�� »
| 5.21�F�����H |
|
�_�̂������œ���Ō������i2012�N5��21���j�B

|
Posted by hajimet at 23:55
| Comments (0)
|
| ����������{�� |
|
�V��v�ۂŌ��������́B2011�N8���B

|
Posted by hajimet at 23:53
| Comments (0)
|
| �����Ɗ�Ȃ��n���O�� |
|
갸 �Ɍ����܂����B2011�N7���A�r����ŁB
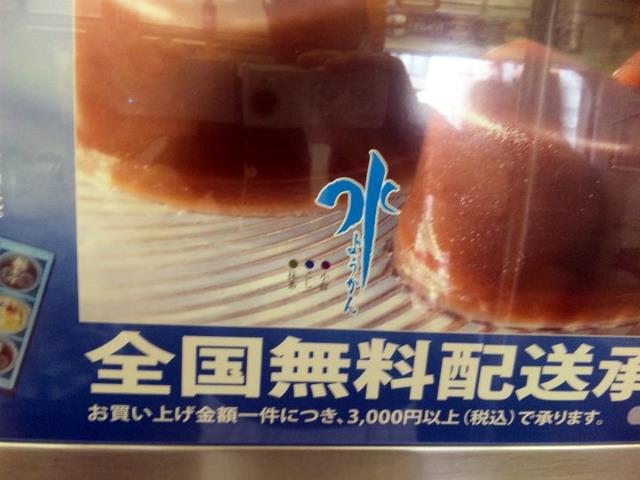
|
Posted by hajimet at 23:48
| Comments (0)
|
| �����Ɗ�Ȃ��n���O�� |
|
IT�ɂ������ʐ^�ł�����ǂ����Ă��n���O���ł��B

|
Posted by hajimet at 23:30
| Comments (0)
|
| �𗬂����A�l�Ƃ��������Ƃ��i�|���A��t����O�ɂ��āj |
|
�c2012�N�A�|���A��t��肪�N�����Ƃ��ɏ��������̂ł��B
�����̂Ƃ���̓��A�������a瀁B�F�X�l���邱�Ƃ����邪�A
�����I�ɑ傫�ȈႢ�����邱�Ƃɂ��C�Â����B
�ؗ��u�[���̑��݂ł���B�ؗ��u�[���̌��ʁA�؍��ɊS����������A
�؍���������l���}���ɑ������B�����āA�����Łu�𗬁v���x���łȂ��A
���ۂɍs����������������؍��̐l���������i����͎����j�B
�����Ȃ�ƁA���̐��{���x���ʼn�����肪�����Ă��A
�����̃��x���ł́u�؍��ɂ���w���̐l�x�v��A�z���邱�Ƃɂ���B
�ؗ��u�[�����n�܂�O�́A�؍��ɍs�����l�͑����Ă��A
�����̐l�����s�ł̐ړ_�ł����Ȃ������B�l�̐ڐG�ł͂Ȃ������̂��B
���ꂪ�A�u�؍��ꋳ���́�������v�A�u�H�̍u���́����搶�v��
�C���[�W���ς�����̂͑傫���̂��낤�B�d���̊W�łȂ��A�l�I�ȊW�Ƃ��Ăł���B
�܂�A�p�C�v�������āA����I�ȂƂ���܂ł͂����Ȃ��ƌ������ƂɂȂ�B
����ɑ��āA�����̏ꍇ�B
�܂��A�����܂ł̊W�������Ă���l�͑����͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�d���◯�w�ȊO�̑����̐l�ɂƂ��āA���ۓI�Ȓ����ł����Ȃ��B
������猩�Ă����ۓI�ȓ��{�ł����Ȃ��B
���̈Ⴂ���A����́u�Η��v�ɑ���l�X�̔����̈Ⴂ�Ɍ��т����Ă���悤�Ɏv���B
����̐��{�́u�w���v���傫�����Ƃ����邪�A
���ꂾ���ŁA���̖\���܂ł͐��������Ȃ��悤�Ɏv������ł���B
���������A�؍��ł������^���͂����Ă��A�\���Ɍq���������Ƃ��L���ɂȂ�
�i�A�����J�ɑ��Ă͂��������j�B
��͂肠����x���{�ɒm���Ă���l�����āA
���̐l�̑��݂��u���[�L�ɂȂ����̂����m��Ȃ��B
�ݓ��̑��݂��傫�������̂����m��Ȃ��B
�e�ʂ����{�ɂ���킯������c�B(2012�N9��28���AFB���e�L���j
|
Posted by hajimet at 23:33
| Comments (0)
|
| ���̂��K�����Ɓi�b���Ă݂悤�؍���𒆐S�Ɂj |
|
NHK�����̃t�@�~���[�q�X�g���[�Łu������v�t���������Ă����B
�Ō�ɉԗɌ���Ă��錾�t�Ť
�����Ɂu��A�j�A���v�Ƃ������t������ƌ������Ƃ�����Ă����B
�ŏ��͎t���ɒ����ɏ]���u��v�B���̒i�K�Ŏt�������z���悤�Ƃ���
���̂��߂̑��̐l�ɂ����Ă��炤�u�j�v�B
�����Ď��������̐��E�����u���v�ƌ������Ƃ��K�v���ƌ���Ă����B
�ǂ̕���ł������Ȃ̂��낤�B
2013�N1��27���B�u�b���Ă݂悤�؍���@���������v�̑��������B
�ʔ������ƂɁA�w���҂̃J���[���ǂ��o�Ă���B
�R���N�[��������w���̃|�C���g�������ɂȂ�͂��Ȃ̂ɁA�Ȃ��łĂ���̂��B
�����Ƃ����ڎw���Ă���̂ɁA�ʔ������̂��Ǝv���B
���Z���̏ꍇ�A�����Ƃ̋�������w����Љ�l��薧�ڂɂȂ�̂ŁA
�����ґ�����̉e���͑傫���B
�K�����Ƃ��āA�܂��́A���̐搶�̕��@�Ŋ؍�����w�K���Ăق����i���j�B
�����đ��ƌ��������Ȃ�A�V�����搶�̌��ł���ɏ�̐��E��ڎw���Ăق����B
�w�K��i�߂邤���ɁA���Z�̎��͂悭������Ȃ��������ǁA
���̐搶�̐����ł悭���������Ƃ��A���̂Ƃ��A�悭������Ȃ����������̎d�����
���̐搶�ɕ�������悭���������ƂȂ����ŗǂ��킯���i�j�j�B
���炭���𑱂��āA���̂Ƃ��A���̐搶�������Ă����̂́A
�u�����������Ƃ��A���������ړI�Ō����Ă����v�A�Ƃ����Ƃ���܂ŗ������Ă��炦��A
���������Ƃ��Ă͖{�]�B���łɁA�����̐��E��z���Ă��邱�ƂɂȂ�i���j�B
���̂��K���ƌ������Ƃ́A�ǂ�ł��������낤�B���݂ɓo�邽�߂̌P���҂Ƃ������B
�����R��o���Ă��A�[�̊K�i���������̐_�Ђ��璭�߂�i�F�ƁA���ォ��̌i�F�͈Ⴄ�B
�ォ��̌i�F���ǂ����Ƃ̕��������B
�������A�ʼn_�ɏ��Ηǂ��킯�ł͂Ȃ��B�����R�ɂȂ�Ȃ�قǑ���̊m���������Ȃ�B
������A�K�C�h���K�v�Ȃ̂��B�K�C�h���Ƃɒ��ӂ���Ƃ���A���[�g�̑I�ѕ��A
�V��Ȃǂf����^�C�~���O�͈قȂ�B
�������A���̃K�C�h�ɂ��ēo��A���̑�햡��m��Ή���ł��o�肽���Ȃ邾�낤�Ǝv���B
���̌�A�ŏ��̓K�C�h�ɋ�������Ƃ���ɏ�낤�Ƃ��邾�낤�i��j�B
�����A���̂������̃K�C�h��F�X�Ȑl�Ƃ̏o��ɂ���āA
�K�������Ƃ��x�[�X�ɂ��Ȃ�����A������������悤�ƍl�����낤�i�j�j�B
���̂����ɤ�����Ȃ�̓o�R�@���m�����邱�ƂɂȂ�i���j�B
�����Ď����Ȃ�̒��]���y���ނ��ƂɂȂ�B
�������A��x�݂���Ƃ��A�J�̎��ɂ͉J�h�肷��ƌ������Ƃ��K�v�B
�łȂ��ƁA���䂵����A���ꂵ�ē|��邱�ƂɂȂ邩��B
|
Posted by hajimet at 23:03
| Comments (0)
|
| ���l�T���X |
|
���l�T���X
1.�w�i
�@�@�\���R
�@�@�@�@���c���̎���
�@�@�@�@�����A���l�̐L��
�@�@�@�@�s�s�̐L���B����܂ł̓s�s�ƈقȂ�u�����s�s�v�̏o��
�@�@�@�@�@���s�s�͎��R�ɂ����B
�@�@�@�@�@�������m�肵�A�����̐������y�����Ƃ������l�w�̏o������
�@�@�@�@�@�@���_���S�̒����̎v�l�ƍ���Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�˃��l�T���X�i���|�����A�M���V�A�A���[�}�Ƀq���g�����߂�j�̔w�i
2.���l�T���X�Ɛl�Ԓ��S��`
�@�l����`�ҁi���A���j�A����ɊS�A↔�_����`�F����A���c�A�����j
�@�@���e���ꕶ���̌�����ʂ����L�P���̃C���p�N�g
�@�@�@�@�l�Ԃ̓��S�X�ňӎv�����킷�̂�����A�w��ɂ���ċ��{�ihumanitasu�j��
�@�@�@�@�@�g�ɂ��邱�����K�v�B
�@
�@�@�y�g�����J�F���e���ꕶ���������A�ߑ�o�R�̕��i�����ɎR������������j�B
�@�@�G���X���X�F�����ᔻ�����w��_��]�x���u�@�����v�v��
�@�݂��Ɂu�s���v�ł���Ƃ��Ƃ̎��o���u�����v�̊ϔO�̔����B
�@�@�@�@�u����������������Ȃ�A���Ȃ��������������v�B
�@�@�@�@�@�@���_�̉��ł̕����Ƃ͈Ⴄ�ϔO�B
�@�@�@�@�u�l�Ԓ��S��`�v�̔���
�@�@�@�@�@�@���\�l
�@�@�@�@�@�@�G��ʼn��ߖ@�̓o��
�@�@�@�@�@�@�@����������������悤�ɋM���ɂ�������͂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�_�r���`�A�u�Ō�̔ӎ`�v�̉��ߖ@�F
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̏œ_�̓C�G�X�Ɍ������Ă���悤�Ɍ����Ȃ���A�����ɂ���Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C�G�X�̔w��Ɍ������i���肰�Ȃ��œ_�����炷�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���_���S�̐��E���痣�ꂫ��Ȃ��A��������ߐ��փp���_�C����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �ς��Ƃ��ŁA�����炳�܂ɐl�Ԓ��S��\���ł��Ȃ�����B
3.�܂Ƃ߁F�ߑ�v�z�̓���
�@���l�T���X��@�����v���o�����ʐ���
�@�i1�j�l�Ԓ��S�F�{�b�e�B�`�F���u�t�v�͊G�̒��Ɂu�x�v�̏ے���`���A�l�Ԓ��S�����肰�Ȃ��\���B
�@�i2�j�l�̎��R
�@�i3�j�����I���_�F�o���Ɗ��o���d���B�����Ɛ��w�I�v�l�B
�@�@�@�@�_�r���`�F�@�����Ŏ��R���w�Ԃ��Ƃ͋������ƌ����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�Ԃ̓��̂̉�U�}�������ō��A����Ɋ�Â��āA
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�Ԃ���Ă����悤�Ƃ��Ă����B
�@�i4�j�i���j�ρF���R�̐����ƎЉ�W�ɂ���l�ނ͔��W�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̍l�������邩��i����͕ʂƂ��āj�����͊J���ł����B
���̂��ƁA�x�[�R���A�f�J���g�ցB
|
Posted by hajimet at 12:02
| Comments (0)
|
| �C�X�������Ƃ��̉e�� |
|
�C�X�������Ƃ��̉e��
�P���F�C�X������
�@�@�@�@�C�X�������@1����
�@�@�@�@���̉e���@�@0.5����
�����F
�@���{�ł͓���݂����Ȃ�
�@�@�A�����J�̎���
�@�@���Ă̎��_���o�ăC�X�����̂��Ƃ����{�ɗ�������̂ŁA�C���[�W����B
�@�@���ہA���z�͈͂��L���B
�@�@�@�@�@�@�@���݂ł���A�t���J�ɐ��͊g�����i�g�����̏@���͂��܂�Ȃ��j�B
�@�@�@�@�@�@�@�����̓C�x���A�����܂Ő��͌���ł������B
�@�@�@�����ꂾ���M���₷���@���ł���ƌ������ƁB
�W�J�i1�j�C�X�����������̔w�i�ƃC�X������
���˒n�A�A���r�A�����F�V�q�����n��B�������Ƃɑ��_����M�B
�@�@�@�@�@�@�������m�̑����������A���̉������ۑ�ɂȂ��Ă����c�@�B
���b�J�F�i�n���}�h�̐��n�j�������Ղ̗v�ՁB�_�a������A���n���}�h�ꑰ���x�z�B
�@�@�@�@�@�@�������������Ƃɂ�������x�z�̑Ŕj���ۑ�c�A�B
�@
�@�@�@�@�A�A�c�����������ɕ�点��V�v�z�����߂���i���n���}�h�̎���j�B
���n���}�h�F40�̂���A�ߗ쌻�ۂɂ���Đ_�̌��t�����Ƃ����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�Ȃ��a���҂����o��������B
�@�@�@�@�@�@�@�@622�N�A��_���̃��_�����̋������f�B�i�ɐ��J�B���̌�630�N�Ƀ��b�J�ɖ߂�B
�C�X�������̓���
�@��A���i���������C�X�����́u��ΐ_�ւ̋A�˂��v���Ӗ�����j�B
�@�@�@�_�iAL Lah��The God)�͒��z�I�ȑS�m�S�\�̗B��̐_�ŁA���邱�Ƃ��o���Ȃ��B
�@�@�@�@�������q�͋֎~
�@�@�@�i����c�~�A���{�l�`�c�~�A�ꍇ�ɂ���Ă͎ʐ^���B����ŁA�A���r�A�����͔��W�j
�A���l����
�@�@�@�A���[�̑O�ł͂��ׂĂ̐l�������B
�B�M�k�̎��H�`�����Z�M�܍s
�@�@�Z�M
�@�@�@�B��_�i�A���[�j
�@�@�@�V�g�@�K�u���G���i�W�u���[���j
�@�@�@�o�T�i�[�T�j
�@�@�@�@���[�Z�̌�
�@�@�@�@�_�r�f�̎���
�@�@�@�@�C�G�X�̕�����
�@�@�@�@�N���A�[���i�����Ȃ��́A�A���r�A��̂݁j
�@�@�@�@�@���A���r�A�ꂾ��������A�R�[������������n��̓A���r�A�ꂪ���ʌ�ɂȂ�B
�@�@�@�@�@�@�@�u�[�T�̖��v�F�����A���[�̌��t��`����ꂽ���_�����A�L���X�g���B���ʈ����B
���Ɍ܍s�̒��ŁA��q�A�f�H�𒆐S�ɘb���B
�@���b�J�̕����̕�������ʎ��j�A
�@����̃I�����s�b�N���f�H�̎����ɓ�����A���V��c�ŋ����o���B
��q�F�u�A�U�[���v������B
�W�J�i2�j�F�C�X���������ƃ��[���b�p
�C�X���������F�l�X�ȕ����������ꂽ��A�e����^���邱�Ƃ��o���镶��
�@�@�@���������̎v�z����A�C�X�����������Ƃ���Ƃ̌��Ղ��\�ɂȂ邩��B
�@�@�@�@�@�@��������u�A���W���Ɩ��@�̃����v�v�Ȃǂ������Ă������B
�@�@�@�@�@�@���{�ɂ̓C�`�W�N�A�U�N���A���q�A���i�Ȃǂ�������
���[���b�p�Ƃ̐ڐG
�@�@�@�@�E�}�C����
�@�@�@�@�\���R�i12���I���l�T���X�j�A���R���L�X�^
�@�@�@�@�E�B�[����͂ɂ��g���R�u�[���Ȃ�
�@�@
�@�@�@�@�E�C�X�����o�R���l�X�ȕ��������[���b�p�ɓ���B
�@�@�@�@�@�@�M���V�A�N�w�A
�@�@�@�@�@�@�����i����܂ł̓p�s���X�A�r�玆�j�A�Ζ�A���j�ՁA�u�[���v�Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�@������p�A�@�����v�A�A���n���A��q�C����A�㐔�w�̔��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�C�X�������Ŕ��B�����B���p���Ȋw�̔��B�B
�@�@�@�@�E�R�[�����ł͉��y�͋֎~�B
�@�@�@�@�@�@�������A�A�U�[���̐����������[���b�p���y�̐����ɉe����^����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�����ꂪ�Ȃ���A�|�b�v�X�͑��݂����Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�g���R�u�[���F�g���R�̑Ŋy�킪���荞�ށB
�@�@�@�@�@�@�@�@�����ꂪ�Ȃ���A����̃o���h�͐��������Ȃ��B
�@�@�@�@�E���[���b�p�ɂȂ��T�O�����[���b�p�ɗ����B
�@�@�@�@�@�@�A���J���A�A���R�[���̂悤�ȒP�ꂪ���[���b�p����ɑg�ݍ��܂�Ă������B
�@�@�@�@�@�@�@������炪���l�T���X�ɂȂ������B
����́A���̂悤�ȃ��l�T���X�̎v�z�w�i�B
|
Posted by hajimet at 11:41
| Comments (0)
|
| ���{�����i���q����܂Łj |
|
���{����
�P���F����
�{���F�O��ʎ�S�o��ʂ��āA�����v�z�����{������Ă��邱�Ƃ������B�����ŁA�{���ł͓��{�łǂ̂悤�ɕ����v�z��������Ă������A�{�i�I�ɓ��{�������W�J���銙�q�����̓����܂ł����邱�Ƃɂ���B
1.�@6���I�Ɏ�e
�@�@�@�����͔ː_�Ƃ��Ď�e�����i�h�䎁�ƕ������j��������L�ɂ��邱�ƂɌq����
�@�@�@�@�c�a�ғN�Y�F���̂悤�ȓ��{�̕������u�����̏d�w���v�Ƃ������t�Ŏ������B
2.�@�������q
�@�@�@�\�����̌��@�i�}�v�j
�@�@�@�O���`�`�i���`���܂Ƃ߂��Ƃ����j
�@�@�@�u���Ԃ��ꋕ���c�v
�@�@�@�@cf.�@���{��
3.�@�ޗǎ���F����i�썑�j�����B
�@�@�@���̍��͕����y�B���͕��Ɂi���Ӂj�̉��g�B���ߐ��x�ƃy�A�̍l��
�@�@�@�@�����V�c�i�������A�啧�Ȃǁj�A�Ӑ^�i������x�j�A��s�Z�@(����)�B
�@�@�@�@�@(���̕ӂ͐V�������Ɗ֘A�Â��Ęb���Ă��ʔ����c
�@�@�@�@�@�@�ޗǂ̑啧����ḎՓ߂Ƃ������Ƃ́A�؍��Ŏ嗬�̉،��o�̉e���j�B
4.�@��������F�������v�����߂镧��
�@�@�@���ߐ��̊ɂ݁��썑��茻�����v�����߂�B�Ώۂ��M�����珎���ցB
�@�@�@�@�Ő��F������J���A�Ǝ��̎�����x�i����6����ɋ��j�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�،o�𒆐S�Ɂu��؏O�����L�����v���Ƃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ȃ��@�،o�����������߁k�̌��t�͎g�킸�Ɂl�ɂ��ĉ���j�B
�@�@�@��C�F�^�������Ɋ�Â������������N�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�F���̌������x�z�������@���M���s���i������o�Ă����疧���n�j�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�u���R�v�Ɓu�F���v�̗Z����ڎw�����o�����{�ɂ������i���ȏ����j
5.�����̓y�����F
�@�@�@�i1�j �_���K���F�_�{���A�C�����Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�{�n��瑐��F���ɂ��E�q�A�_�Ƃ��Ďp��ς��Č���遁����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�]�T�̂���N���X�́u���̕���v�̕Ґ��j�B
�@�@�@
�@�@�@�i2�j���@�v�z�F�Љ�s�������q������
�@�@�@�@�@�@���{�ł�1052�N���疖�@�Ƃ���A�������ʂ͂���ɂ���ĕ����@�P���������Ă�B
�@�@�@�@�@�@�P������r�̒��̓��Ɍ��āA���ɂ͈���ɔ@��������B��y�M�̂�����B
�@�@�@�@�@�s���̐��Ɍ����łȂ��A��y�ɂ����낤�Ƃ�����
�@�@�@�@�@�l�����ʂƂ��́A�呛�����Ĉ���ɂ����}�������Ɠ`������B
�@�@�@�@�@���i����ɐ��j�⌹�M�i�}���q�y�A�Ӌ���y�j�F����ɂւ̋A�˂��Ƃ��A
�@�@�@�@�@�@�R�F�u�얳����ɕ��v�̂ݏ�����Ηǂ��Ƃ�����y�@���N�����B
�@�@�@�@�@�e�a�F�����@�R�A��y�^�@���N�����B
�@�@�@�@�@���@�F���@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�̐��A�@�،o�ɋA�˂��A�u�얳���@�@�،o�v��������Ηǂ�
�@�@�@�@�@��y�M�F���̂���̓��A�W�A�ɋ��ʂ̐M�i���A�V���̖����j�B
�@�@�@�@�@���@�̎v�z�F���{�Ǝ��B
��������嗤�̕��G�ȋ��`��P���������Ƃ���ɓ���������B
�@�@��ڂȂǂ�������u���̂�����v�~����Ƃ������{�̎v�z�̓������痈��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���ȏ����j�B
|
Posted by hajimet at 11:15
| Comments (0)
|
| �ʎ�S�o�i���v�z�Ɠ��ł̕ϑJ�j |
|
�ʎ�S�o
�P���@����
�@�@�@�@�@�C���h�v�z
�@�@�@�@�@�J�[�X�g���ƃo��������
�@�@�@�@�@���ɂ̐��U
�@�@�@�@�@���ɂ̌��ƌ��n����
�@�@�@�@�@���h��������������
�@�@�@�@�@��敧���i2���ԁj
�@�@�@�@�@�ʎ�S�o�i���v�z�Ɠ��ł̕ϑJ�j�c�{��
�@�@�@�@�@���{�����i���q�ȑO�j
�ڕW�B�ʎ�S�o��ǂ݉������ƂŁA���v�z�i���K�j���ǂ�����Ă��邩���m�F����Ƌ��ɁA
�@�@�@�@�ʎ�S�o�������؊e���łǂ��������Ă��邩�A
�@�@�@�@���ɓ��{�łǂ��ϗe���Ă������̂��ɂ��Ċw�K����B
�@�@�@�@�@
1.����
�@�u�ʎ�S�o�v�̏����Ă���v�����g��z��A��������B
2.�W�J(1)�@
�@���d�ʎ�g�������S�o�̉���F���v�z���ǂ��ǂݍ��܂�Ă��邩�B
�@�@4���I�������B
�@�@�ώ��ݕ�F=�ω����V���[���v�g���Ɍ��`��
�@�@�@�@���ׂĂ���ł��邱�Ƃ��ω��͌�������A����͐F������Ƃ������Ƃł���B
�@�@�@�@�Z�����Z�����Z�����u���v�ł���A�l�������]�X���u�������ɓǂ݂Ȃ�������v
�@�@�@�@����ɁF�ʎ�g�����ɂ�邽��
�@�@�@�@�@�@�@�A�m�N�^���T���~���N�T���{�_�C�i���̏�Ȃ����j��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O���F���S�Ȍ��i�O�����S�k�p���Sum�A���=���l�B
�@�@�@���̓��͈̑�ȃ}���g�����^���ł����āA�M���e�[��������B
�܂Ƃ�
�@�E���̂��߂̓����c�v�����g�z�z
�@�u�ʎ�S�o�v�̍\�����܂Ƃ߂����̂ƁA�u�@���䕷�v�Ŏn�܂�ʎ�S�o�A�G�����̔ʎ�S�o�B
�@�@�T���X�N���b�g�ł��ꕔ�������A
�@�@�@�{���ɃA�m�N�^���T���~���N�T���{�_�C�Ƃ��A�}���g���Ƃ��A�K�[�e�[�ƌ����Ă��邱�Ƃ��m�F�B�@�@�@�@�@
�@�@�@���{�̔ʎ�S�o�A�؍��̔ʎ�S�o������i2�N���X�͐��肠����j�B
�@�E�����Ŕʎ�S�o�̂Ƃ炦�����قȂ�i�������̂��Ⴄ�@���ƍl���������悢�j�B
�@�@�@�E�����F�T�Ƃ��āB
�@�@�@�E�؍��F�����̐^������������o�T�Ƃ���
�@�@�@�@�@���T�̎v�z�����A�ō��̒m�b�ݏo�������̌o�T�Ƒ������Ă���B
�@�@�@�E���{�F(1)�T�̂��߁A(2)�_���Ƃ̗Z���A(3)�}���g��������������p�Ƃ����B
���{�̏ꍇ�A
(1)�@�o�T�����ǂ݂œǂށB
�@�@�@�����ł͂�����x�����Ă��ĈӖ��������邪�A���{�ł͂킯�̕�����Ȃ����́B
�@�@�@�킯��������Ȃ�����s�v�c�Ȃ��́��u�L��A��v�����ƕ߂炦�A
�@�@�@�����ɗ�͂�����ƍl����(�_���Ƃ̗Z���j�B
(2)�@�ʌo�i���{�Ǝ��̂��́j�A
�@�@�@�������^���̏����Ă����ʎ�S�o���g����I�ȁu�p���[�v�������̂ƍl����B
�@�@�@������Ă���ʎ�S�o���̂��u�p���[�X�|�b�g�v�Ȃ̂ł���B
�@�@�@������A�ʌo�����ăp���[���邱�ƂɂȂ�B
(3)�@�}���g���̎�p�F
�@�@�@�Ẵe���r�ŕ��f����鏜��V�[���ŏ�������o�T���u�ʎ�S�o�v�B
�@�@�@����������ė��ǂ��o���B
�@�@�@�@�@���u�ʎ�g�������v�̗͂ɒ����������́i�����n�̗���ɂȂ�B�j
����F�ʎ�S�o�����{�ł͓Ǝ��̂��̂ɂȂ����悤�ɁA���{�����̓����͉����B
|
Posted by hajimet at 10:48
| Comments (0)
|
| �R�@�����v�ƉB��L���V�^���i2012�N�x�@�ϗ����Ƃ��) |
|
�u�R�@�����v�ƉB��L���V�^���v
�ȖځF�ϗ��i�s����ꍂ���w�Z2�N3�N���X�j�@1����
�P���F�L���X�g��
�@�@�@���_�����A
�@�@�@�C�G�X�A
�@�@�@�C�G�X�̎��ƌ��n�L���X�g��
�@�@�@�A�E�O�X�e�B�k�X
�@�@�@�X�R���N�w
�@�@�@�{���i���ʕҁA�܂Ƃ߁j
�@
�ڕW
�@�L���X�g�������{�ɂ����炳�ꂽ�B����͑R�@�����v�i���@�����v�j�̌��ʂł���B�U�r�G����C�G�Y�X��ɂ���Ă����炳��邪�A���̂��Ƃ����{�ɂƂ��ėL���ɓ������B����ŁA�L���V�^���֎~�߈ȍ~�A�M��ۂ����l�тƂ��������A�ނ�̏@���͎���Ɂu�y�����v���ĕϗe���Ă������B�ϗe���A���^���c�����ƂȂǁA�ٕ����̎�e�̂�������A�U�r�G���A�B�ꂫ����^����ʂ��čl���邱�Ƃɂ������B
1.����
�@�@�����̃J�g���b�N�̕��s�i���ׂĂ̌��Ђ�����ɁAcf.�g�}�X�E�A�N�B�i�X�j
�@�@�@�����^�[�̏@�����v�i1517�j�B
�@�@�@�@�@�J���o���̗\����F���ƁA���Z�Ƃ��L���X�g���̑�����x���闝�_�ł����B
2.�R�@�����v(���@�����v�j�B
�@�@�J�g���b�N�̑��̉��v�i1545�@�g���G���g����c�j
�@�@���^�[�̋͂���\���N��i1534�j�ɃC�G�Y�X��ݗ��B
�@�@�@�@�U�r�G��(1506-1552)�F���N�l7�l�̂����̈�l�B
�@
�@�C�G�Y�X��F�C�O�ւ̐鋳���l����B
�@�@�@����āA�A�W�A�i�o�i���҂ňقȂ�j�B
�@�@�@�@�@��ā@�F�����o��A�C���t���G���U�ŏZ�������ʁA���łȍ����Ȃ����A���n
�@�@�@�@�@�A�W�A�F���łȍ��i�����A���N�A���{�j���u�A���s�v�������Ȃ��i�S�A�Ȃǁj
�@�U�r�G�������ȋ]���̐��_�i�g���G���g����c�A���ȋ~�ώQ�Ɓj�ŃS�A�ɍs���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�S�A�����W���E�ɉ�������ɏ㗤�i���^�[����40�N�����Ă��Ȃ��j�B
�@�@�@�@�@�@�@�@���ˌo�R�ŋ��s�܂ōs��(���m�̗��̍����œV�c�ɂ͉�Ȃ��j�B
�@�U�r�G���͓��{�l�������]�����Ă������A���n���ւ̓�����܂Ȃ������B
�@�@�@���ً̈��k�ƈقȂ��������q�����Ȃ�
�@�@�@�@�@�E�_�ЁF�֍��Ȃǂɐ_�����낵�āi�˂��j�A������^������ǂ��ċA���Ă��炤
�@�@�@�@�@�@�@���M�炸�Ɏ���ĖႤ
�@�@�@�@�@�E�����M���Ă����i�ŏ��A�_���u����v�Ɩ��B�̂��Ɂu�f�E�X�v�ɕύX�j�B
�@�@�@�@�@�@�@���U�r�G���̌��
�@�i���킦�āj�C�G�Y�X������n�̏K�����d�����Ȃ���z�����邱�Ƃ���̕��j
3.���{�ɂ�����L���X�g���̊g��
�@�@�����{�𒆐S�ɃL���X�g���͍L�܂�A�R���M�I�A�Z�~�i���I�A������������B
�@�@�Z�~�i���I�ł̓��e����A���y����Ȃǂ��s���A���Ȃ萬�ʂ��������B
�@�@�I���K�����܂ߐ��m�y��͂��̎������Ȃ���{�ɓ����Ă��Ă���B�@�@
�@�@���V�������g�ߎg�ł̓��[�}���c�̑O�����̂������ɉ̂��Ă���i���̉̂�����j�B
�@�@�@�c���{�l�ɂƂ��ċ��Ƃ����u�t�@�A�V�v�̉������m�ɏo���Ă���ƌ������Ƃɂ��Ȃ�B
�@
�@�@�@�@(�G�k�j�����̂��ق��O���l���[�\���͓��{�l�ɂ���2�����o�����邱�Ƃ�
�@�@�@�@��]�I���ƔY���A�����ł͂Ȃ������B(���ł��s����ȉ��j�B
�@�@�@�@�������Ƃ����狳�����������낤�B
4.��
�@����̕�����3����B�i�v�����g���g���Ȃ���j
�@�@(1)���@
�@�@(2)�M�ێ��i�B��āj�B
�@�@�@�@�B�ꂽ�W�c���m�̐ڐG�͂Ȃ����A�V�������͓̂����Ă��Ȃ��B
�@�@�@�@�����R�ɕώ����y�����B
�@�@�@�@�@�@�i��j�����F���o���グ�Ă���e�ŁA���o�̌��ʂ������u���炵��v�������A
�@�@�@�@�@�@�@�@�\���˂̗l�Ȍ`������������������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ꂪ���������Ӗ����͎���ɕ�����Ȃ��Ȃ�B
�@�@�@�@�@�@�u���炵��v�̂Ȃ��ɂ̓f�E�X�A�A�x�}���A�A�L�����A�P���h�Ȃǂ̌��t���c���Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̈Ӗ��͕�����Ȃ��i���̐��̂͂��Ȃ蕪�����Ă���j�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������������Ȃ��Ƃ�����������J�邱�Ƃ��o���Ȃ�����Ɗo���邾���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�u���炵��v�̈ꕔ������j
�@(3)�C���[�W���c���B
�@�@�@�@���ɂȂ萹�̂��̂����Ƃ͏o���Ȃ��Ȃ�B
�@�@�@�@���m�y����L���V�^���Ƃ̊W�Ŋ��S�ɚʂ����B
�@�@�@�@���ՂȂǑ��̊y��Ŕ��t�������������t���āA�{���̋Ȃ��C���[�W����B
�@�@�@�@�@�@�i�R�[�h�i�s�����Ŗ{���̋Ȃ�A�z����悤�Ȃ�>�́j
�@�@�@�@�����̂����ɁA���̂Ƃ����C���[�W�͏����A���t�������c��B
�@�@�@�@�@������������Ȃ�ⵋȁu�Z�i�v�B
�@�@�@�@�@�@�@�@(���̋ȂƁA�ՂƏd�˂����t�A�Z�i����������������j�B
5.�܂Ƃ�
�@�@���ǁA�ٕ����ƐڐG����Ƃ��͕ϗe���Ď������B
�@�@�@(�����W�[���Y�ł����{�A�؍��A�����ł͗������Ȃ������Ⴄ�j�A
�@�@�L���X�g���̏ꍇ�A�f����o�Ă��邩��A�啝�ɕϗe���y��������B
�@
�@�@���̏ꍇ�ł��A�u��`�q�v���ǂ����Ɏc��B
�Ō�ɁF�U�r�G���̖��A���{�ɖ@�w�A�_�w�A��w������������w����邱�ƁB
�@�@�@�@�@�@��1928�N�Ɏ����F��q��w
|
Posted by hajimet at 09:50
| Comments (0)
|
| 2012�N�x�؍�����Ɓi�n���O����ǂ����j |
|
�n���O����ǂ����B
�ΏہF�n���O�����w�юn�߂�����̐��k�i2���ԁj
�@�@�@�@아야어여���I���A�L�������A�p�b�`���ƃ��G�]�����o�����Ƃ���B���6�����{�B
�@�@�@�@�i�������A�Z�����ɂ͐G��Ă��Ȃ��j
�ړI�F���͂œǂނ��ƁB
�@�@�@�@�Ӗ��͕�����Ȃ��Ƃ��A�ǂނ��Ƃ͏o���邱�Ƃ�����������B
�@�@�@�@���n���O���̒蒅�̑����B
���ށF����J�A�V�h�A���C�ف@I LOVE YOU
�@�@�@�@���������A���������@���т܂�q�����̃e�[�}�i���G�]�����قƂ�ǂȂ��j�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �A���p���}���̃e�[�}�i������̕����ȒP�j
���ƁF�̎����������v�����g��z�z
�@�@�@ ���@�t���������̂��A�ǂɕ����A��s���J�i�_���\���g���ēǂ܂���B
�@�@�@�ǂݎ�������̂���s���i���邢�͈Ӗ��̓Z�܂育�ƂɁj���ɏ�������
�@�@�@�@�@�������ł̓J�^�J�i���g���i�{���ɓǂ߂Ă��邩�m�F���邽�߁j�B
�@�@�@ ��s���ACD�iDVD�j�����A�����Ă��邩�ǂ����m�F������B
�@�@�@�i�����Ă���A����Ă���A�悭������Ȃ��k�������\�͂��Ⴄ�̂Łl�j
�@�@�@�Ⴄ�ꍇ�A�����Ⴄ�̂���������B
�@�@�@I LOVE YOU�̏ꍇ�A�@�����A���������o�Ă���̂ŁA���ȏ����g���Đ����B
���ʁA���z�@�@�E�ꐶ�������g���k�́A�\���g��Ȃ��Ƃ����悻�͓ǂ߂�悤�ɂȂ�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�������ǂݎ�������ƁA������������v���邱�ƂŁA
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���Ƀn���O�������œǂ߂�i�p��ƈႤ�j���Ƃ���������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���n���O���ɑ����R��������B
�ʐ^�͓���J���Z�Ɗ����������Z�i2012�N�͎B�e���Ă��Ȃ��̂ŁA2011�N�̂��̂��g�p�j
����J���Z�i2011�N�A����������̎��v�Łj
.jpg)
�����������Z
.jpg)
|
Posted by hajimet at 13:56
| Comments (1)
|


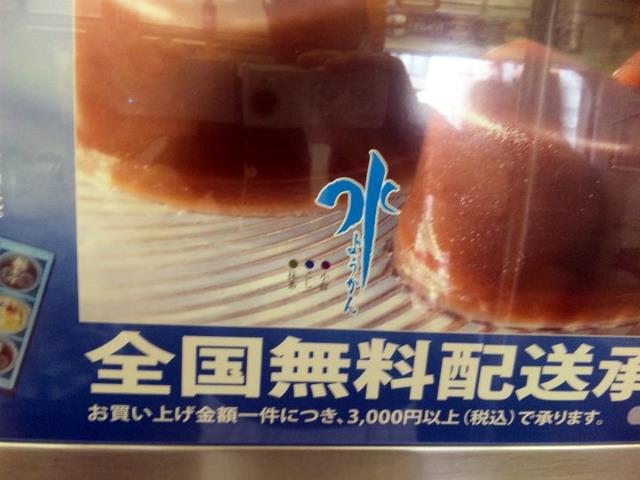

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)