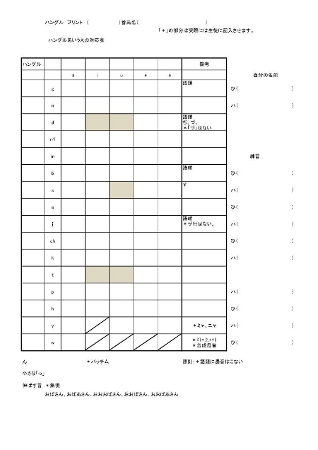高等学校では様々な科目が置かれている。
その教科、科目は文部科学省が定める学習指導要領で決められているのだが、
それ以外にも学校設定科目として設定できる科目もある。
外国語の場合、文科省の定める共通必修科目である外国語(教科)の
英語(科目「コミュニケーション英語」など)に代わる学校設定科目として、
ドイツ語、フランス語、中国語などと共に韓国語を置くことが出来る。
この場合、学習内容は英語に準ずる科目として扱われる。
学習指導要領の外国語教科に英語しか出ていないため、
学校設定科目とするのだが、
要するに、英語でない外国語を、英語の代わりに必履修科目として学ぶと言うことになる。
一方で、外国語の必履修科目を英語にした上で、
さらに韓国語などを置く場合には、それは学校設定の選択履修科目、
いわゆる「第二外国語」になる。
「第二外国語」は、生徒にとっては履修しなくてよい科目だから、
教えるにはまず、それを学ぶ意義が問題となる。
高校は後期中等教育であって、大学の高等教育とは目的が異なる。
教科、行事、部活動などの活動を通じて人格の形成に資することがその目的だからである。
(これらはどれも学習指導要領に掲げられているものである)
その中で、どう位置づけられるかが大切になるのだ。
先日、以前からお世話になっている元校長先生から手紙が来た。
…Aさんを覚えいてますか?K大学に入ったのですが(ここまでは知っている)、
「あなたに教わったハングルが人生のスキルとなり、韓国人と結婚。
いまはソウル暮らしだそうです」と書かれていた。
Aさんは在日だったが、在学中はそれを隠そうとしていた。
韓国政府の交流事業で韓国に連れて行ったこともあったが、
そのときも韓国の出入国審査のときに他の生徒に分からないように手続きをさせた。
都羅山展望台に行くときには、パスポートを提出させられたが、
日本と韓国の旅券の色が同じだったので事なきを得たという思い出もある。
その後も、
センター試験の時に通名と本名で願書を出したのに、
本名で受験票が届き相談に来たこともあった。
受験番号では、今名乗っている名字と違う頭文字のところに座らなければならないからである。
そのくらい、在日であることを隠し通そうとしていた生徒だった。
きっと、本人自身のアイデンティティが確立できず、
その面での悩みが大きかったのだろう。
一般に、高校の時期は発達段階的にアイデンティティの危機に直面するといわれる。
実際に、自分がどういう存在か悩む生徒は良く見る。
在日の場合は、歴史的、社会的背景もあって、日本人以上にその悩み大きいのだと思う
(当事者でないだけに、これ以上文章で表しきれない)。
そういう生徒のなかに、(多分)そのことで荒れたBさんもいた。
Bさんのクラスでは、2年間世界史、政治経済を担当したが、
Bさんは徹底的に私を避けていて、朝鮮の話が出た途端に教室から出て行くほどであった。
(今は通名でなく、民族名で活躍していると聞く)
そういう煩悶に近い悩みの時期を通過して、本人の中で答えが出たのだろう。
自己のアイデンティティが形成されたのだ。だが、そのきっかけが自分の授業だったとは…。
韓国語の授業は生徒数も少なく、
普通の授業よりも生徒との距離が近くなる。
もちろん、社会科の授業とこちらのスタンスは変わらないのだが、
そうれはあっても、10m近く先まで生徒がいる教室と、
1m50センチの距離に全員がいるのではお互いに受け取りすることが違ってくる。
Aさんもそういう環境の中での生徒だった。
その人の人生に影響を与えて、幸せをつかんだという情報はとても嬉しいことだ。
だが、それだけに自分の気持ちを引き締めなければならないとも思う。
韓国語に限らず、どの授業でも同じなのだが、
韓国語の場合、高校で初めて受講する科目であるため、
特に刺激が大きいのだと思う(担当する範囲で同じような科目は倫理)。
他の科目は曲がりなりにも近い科目を勉強していて、
生徒なりの科目に対するイメージが出来ているからである。
韓国語も外国語科目として、英語教育と同じイメージを持っている生徒が多い。
そのイメージを崩しながら、一定の目標に向かって授業を構成していく。
授業の中で教室の状況に対応しつつ、
韓国に関して学んでほしい扉を、さりげなく準備している。
もちろん、こちらは扉を作って仕掛けているだけで、
生徒が気づいて開けてくれれば本望である。
Aさんは、たまたま、そういう問題意識があったから、
アイデンティティについての扉を開けることが出来たのだ。
そういう素質があったのだ。だから、今があるのだろう。
そういう点から、高校教師のは役目は、
その生徒の人格形成のための触媒だということになろう。