| 2014年3月4日 |
| チヂミ、トッポギ作り |
|
2014年3月4日、六本木高校ハングル中級。3名。 |
|
Posted by hajimet at 21:15
| Comments (0)
|
| 2013年12月22日 |
| 調理実習2013(2)日比谷高校(2013.12.20) |
|
こちらもチヂミとプデチゲ。本だしと書いてあるが、プデチゲはタシダにしてもらった。 |
|
Posted by hajimet at 09:18
| Comments (0)
|
| 調理実習2013(1)杉並総合高校編〔2013.12.18〕 |
|
今年の調理実習、チヂミとプデチゲを作る。 |
|
Posted by hajimet at 09:02
| Comments (0)
|
| 2013年11月30日 |
| ハングル書道 |
|
11月29日:日比谷高校 |
|
Posted by hajimet at 09:04
| Comments (0)
|
| 数字を使ったゲーム |
|
日比谷高校。11月23日。 |
|
Posted by hajimet at 08:52
| Comments (0)
|
| 2013年6月5日 |
| 濃音の練習(各校) |
|
濃音の練習。 「出来るかな(ちょっとにやついて)?、『っっっっっっかり』ていえるかな」。 |
|
Posted by hajimet at 21:46
| Comments (0)
|
| 2013年5月7日 |
| 文字の導入(1) |
|
韓国語の授業を行うときに、避けて通れないもの。文字。最近は自分で学習している生徒も多くなってきたが、それでも大多数は授業で初めて。実際、日本語はひらがな、カタカナで100文字近く、漢字は中学を終えるまでに2000文字以上学んでいるのだから、24文字のハングルは少しの努力で覚えられるのだが、なかなか現実はそうはいかない(理由はいろいろある)。 |
|
Posted by hajimet at 22:26
| Comments (0)
|
| 2013年4月2日 |
| 2012年度韓国語授業(ハングルを読もう) |
|
ハングルを読もう。 |
|
Posted by hajimet at 13:56
| Comments (1)
|
| 2012年度の韓国語授業(新聞を読もう) |
|
新聞を読もう 10月頃 |
|
Posted by hajimet at 11:34
| Comments (0)
|
| 2012年度 韓国語授業より(ハングル書道) |
|
2012年秋 日比谷高等学校(2年)、桜修館中等教育校(4年) |
|
Posted by hajimet at 10:38
| Comments (0)
|
| 2013年3月26日 |
| 韓国語紹介(2時間完結編) |
|
韓国語紹介 |
|
Posted by hajimet at 22:16
| Comments (0)
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
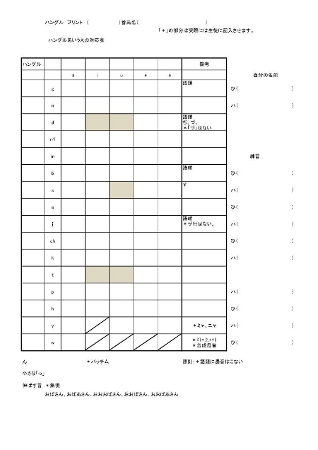
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)