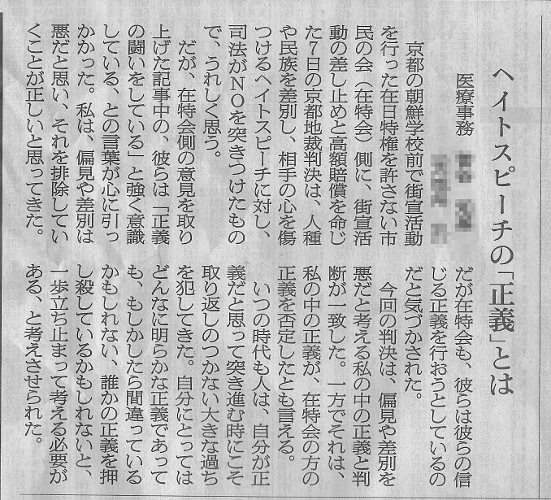« ���Ɓi�ϗ��j | Main | ���Ɓi�Љ�ȁj »
| 2014�N6��26�� |
| �u�Ђ�����Ԃ��v�Ɓu�������肾���v�c����������� |
|
�����̂Ƃ���A�����̖{��ǂ�ł��Ďv�������ƁB ���݂����A���c�l�A�n���ՂȂǂȂǓ�����O�̂��Ƃ��A���͓����R���B ��{�I�ɂ͊����������̏@���ŁA���������ł��������ȊO�͐M���Ȃ��B �������A���{�ł������K�������ł͂Ȃ��B �Ė��V�c���݂̈�Ղ͓����̉e���������Ƃ����w�E�����邵�A �_��v�z�Ȃǂ��������炫�Ă���B �ܓl�ē��Ȃǂ̓������c�͓��{�ɂ͓����Ă��Ȃ�����A �u�����v���̂��̂Ƃ����悤����B�����v�z�A������ ���{�ɓ������Ƒ����Ă�������������Ȃ��B ���Ƃ��Ƃ����m�I�A�j�~�Y��������A ���{�̐_���Ɛe�a�����̂��镔��������悤�����A�����ł��Ȃ��Ƃ��������B �܂��A�����l�̉e���̋�������͛_�c�M�܂߁A�y�n�_�Ȃǒ��ڂ̉e����������B ����Ȃ��ƂׂĂ�����ɁA�ӂƎv�������B �u�Љ�Ȃ̎��Ƃ��āA���ӎ��̈ӎ����v�Ȃ낤�ȂƁB ����������Ζ��ӎ��ł��������̂��ӎ��̐��E�Ɂu��������o���v���ƁB �p��͎��������ɂȂ��T�O��蒅�����A����𗘗p���Ă����B ����͑S�Ă̋��Ȃ̊�b�B�ÓT�A�������܂߂āB ���w��(���́A�ɂ߂Ď��H�I�ȖڂȂ̂����j���k�Ɏ��H�̃C���[�W���킫�ɂ����B ����ɑ��āA���Ђ́A ���R�Ǝ����̎���ɍL�����Ă������E���A���ꂼ��̉Ȗڂ̎��_�ňӎ������Ă����B �����p�̊�b�̏�ɁA�{�l�̐��E���L���Ă�����ƂȂ̂��Ǝv���B �ڍ����ڍ��s�����痈�Ă���n���ŁA���͌܍s�����痈�Ă���i����������j�B �ڔ��������ƋC�����A �P�ɎR����̉w���Ƃ��Ă����ӎ����Ă��Ȃ��������Ƃ��A ����ȏ�̂��̂��ƁA�}���ɍL�����Ă������낤�B �����āA�ڐԁA�ډ��A�ڐ́H�ƂȂ�i�]�ˎ���͖ڐԂ܂ł��������j�B ���������ȖڂȂ̂��ȂƁA����������Ă��ċC����������B ���i�̎��ƂŁA����������Ƃ����Ă���̂����A �����̒��ł͖����Ɉӎ������Ă��Ȃ������B �����̖{��ǂ݂Ȃ���A���̓_����������������B �����Ď��Ƃƃp�������ɍl���Ă��܂����B �؍��W�Ŋ؍��̊W�҂Ƙb�����Ă���Ɓu���j���v���b��ɂȂ�B �����A��y������ �u�K���������j�������K�v�͖����B�ǂ�����Ă����j�ɂ��ǂ蒅���B ��������F�X�Ȗ�����Ηǂ��v�ƌ����Ă����B ���̂��Ƃ͂˂Ɉӎ����Ă���B �����A���ӎ����ӎ�������ƌ������Ƃ��炷��ƁA �������ƌ������A��̓I�C���[�W�Łu���v�������o���̂����d�v�ŁA ���ꂪ�A���ʂƂ��āu������v�Ƃ������Ȃ̂��낤�ȂƊ������B �����悤�Ȏ����A����܂Łu�Ђ�����Ԃ��v�Ƃ������t�ňӎ����Ă����B �������Ǝv���Ă������Ƃɂ��āA�ӎ����Ȃ��������_��^���� �i�Ђ�����Ԃ��āj�A�����]�����Ă����ƌ������Ƃł���B ���̂��ƂƁA�u�������肾���v�́A���_�I�ɂ͓������ƂɂȂ�B �����A�{�l�̒��Ɂu�������������ӎ������̒m�I�E�o���I�~�ρv���Ȃ��ƁA �u�Ђ�����Ԃ��v�͐������Ȃ����ƂɂȂ�ł��낤�B �����u���������Ă������v�������āA��������܂������o���邱�Ƃ� ���ʂƂ��āu�Ђ�����Ԃ��v�ƌ������ƂȂ̂��낤�ƍl���Ă���B |
|
Posted by hajimet at 20:57
| Comments (0)
|
| 2014�N6��22�� |
| ��������j���j�N�̕ۑ��k���N����L�����j |
|
��������j���j�N��ۑ�����ɂ́B |
|
Posted by hajimet at 09:50
| Comments (0)
|
| 2014�N5��2�� |
| ���w�ƍ��Z�̈Ⴂ����(�Љ�� |
|
�����̎��ƁB�ϗ��Ɠ��{�j�B���R�A�������e�͈قȂ�̂����A���̒��œ������Ƃ�`���Ă������ƂɋC�������B �ϗ��́A�u�l�ԂƂ́v�A�u�N���v�Ɛi�B�ϗ��S�̂̓����̖����������Ă���P���ŁA�����b�����Ƃɂ���āA�v�z�ւ̓��@�t��������B�����A�u�₢�����v�������ǖقł�����̂ŁA���̂悤�Ȏv�l�ԓx�ɂȂ�Ă��Ȃ����k�ɂƂ��ẮA��ɂł�����B���̂��߁A�u�����v�Ȃ鐶�k�������B �����̎��Ƃ͂����������k�̑����N���X�i1�N��������A�����������������v�l�ɂȂ�Ă��Ȃ��B���Z���ɒE�炷�钼�O�j�B�ς��ς��Q�n�߂��B�����ŁA �u�Q�Ă���ƕ�����Ȃ��Ȃ�B���������Ă��邱�Ƃ��厖�B�����Ȃ�ǂ��l���邩�A�ǂ����邩����B�Љ�Ȃ͈ËL������D�������Ƃ����l�����邪�A���Z�̎Љ�Ȃ͊o���邱�Ƃł͂Ȃ��A�\�N���e�X���������������Ƃ������Ƃ��o���Ă��d���Ȃ��B�l���Ă������Ƃ����S�v�ƁA���̂悤�Ȑ��k���N�������Ǝv���Č�����B�ܘ_�o����A�������������ƌ����āA�N���Ă���邱�Ƃ͂܂��Ȃ��B ���̎��Ƃ́A�u�t�F�[�g��������������Ęa�e���̊J�`�n�v�܂ŁB2�N���ΏۂŁA2���ԘA�����ƁB���j�Ɨ��j����͈قȂ邩��A�ǂ����Ă����ۓI�Șb�������Ȃ�B�������A������������A�����A�o�ϊ܂߂āA�l�X�Ȃ��Ƃ̗������m��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ߑ㍑�ƂƂƂ��ɁA���m�̍����̐����C���[�W�Â��邱�ƂɂȂ�B ���Ƃ����Ȃ���A �u�o���邱�Ƃ��厖�łȂ��āA�z�����Ă݂邱�Ƃ��厖�B�����Ȃ�A���̏łǂ��l���邩�A�s�����邩�v����B�ƌ�����B���ǂ͐l�̍s���A�l�̍l�����x�[�X�Ȃ̂ł���B�����N���⎖�����o����̂łȂ��A�l���邱�Ƃ���B �����܂Řb���ċC�������B�ϗ��ł����{�j�ł������悤�Ȏ�������Ă���B�v����ɁA�f�ނ��Ⴄ�����B���́A�u�l���邱�Ɓ��C���[�W�Â��邱�Ɓv�͎����̃e�[�}�ł�����̂����ǁB |
|
Posted by hajimet at 00:09
| Comments (0)
|
| 2014�N4��16�� |
| �E�h���Ɗ؍��� |
|
�؍��̗F�l���؍��̃��}�_���Ƃ����Z�J�X���Z�J��H�ׂ��Ƃ��̎ʐ^�B |
|
Posted by hajimet at 10:50
| Comments (0)
|
| 2013�N10��14�� |
| ���`�Ƃ�(����10131009) |
|
�V���̓��e���Ɍf�ڂ���Ă������́B���Ƃŗl�X�ɗ��p�ł���B |
|
Posted by hajimet at 23:20
| Comments (0)
|
| 2013�N9��4�� |
| ���Ă��邯�LjႤ���̕��� |
|
�������N�ϗ����������e���ŁA |
|
Posted by hajimet at 22:11
| Comments (0)
|
| 2013�N5��12�� |
| ���Z�Ŋ؍���������邱�Ɓc�����q�̋ߋ����� |
|
�����w�Z�ł͗l�X�ȉȖڂ��u����Ă���B
|
|
Posted by hajimet at 23:45
| Comments (0)
|
| 2013�N4��15�� |
| �𗬂����A�l�Ƃ��������Ƃ��i�|���A��t����O�ɂ��āj |
|
�c2012�N�A�|���A��t��肪�N�����Ƃ��ɏ��������̂ł��B |
|
Posted by hajimet at 23:33
| Comments (0)
|
| ���̂��K�����Ɓi�b���Ă݂悤�؍���𒆐S�Ɂj |
|
NHK�����̃t�@�~���[�q�X�g���[�Łu������v�t���������Ă����B |
|
Posted by hajimet at 23:03
| Comments (0)
|
.jpg)