 |
漂民屋は江戸時代、朝鮮から日本に漂着した民間人を朝鮮に送還するために、一時収容しておくところであった。厳原の町の港に最も近い所にある。前方が海、両方が川の河口で、厳原の町から数メートル離れている。全体を濠で囲まれているような所である。
江戸時代に、日本も朝鮮も国外へ行くことは禁止されていた。しかし、風向きなどで相手の国に漂着することは少なくなかった。その送還の役割を負ったのが対馬藩であった。対馬以外に日本に漂着した朝鮮の船は、一度長崎に送られ、長崎奉行で取り調べを受けた後、対馬にまわされた。対馬でも調書を取られた後朝鮮へ送り返された。そのときに滞在していたところが、漂民屋だったのである。
風の関係で圧倒的に朝鮮の船が日本に漂着することの方が多かったが、日本の船が朝鮮に漂着することもあった。その場合も対馬藩が送還したが、対馬藩の船は釜山の和館から送還し、それ以外の船は和館を経由せず、直接送還した。対馬藩の機密を守るため だった。
 |
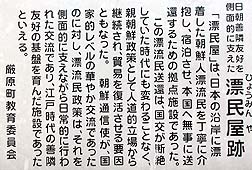 |
 |
| 漂民屋(手前)と厳原の象徴、立亀岩 | 説明板 | 船溜まりと漂民屋(右手奥) |