ビクトリア・ピークとセント・アンドリュース・ピーク
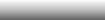
写真−25
2008.4.16
am6:53



欧米の自然保護方式は特権階級のため?‥‥
国際協力機構(JICA/青年海外協力隊員)は、マレーシア政府と大学が共同で行なっているボルネオの総合的な自然環境保全事業に協力して、生物多様性・生態系保全(BBEC)プログラムを実施し、ボルネオの自然環境保全活動に貢献している。
BBECのサイトを読むと、我々が何気なく使用している「自然保護」 の概念は欧米渡来の概念であり、アジアには必ずしも合致した概念ではない、との意味で印象的だったので、以下にBBECのサイトの一部を意訳抜粋してみた。
ボルネオ島の熱帯雨林は、地球上で最も生物多様性の高い地域であるが、その多様性の低下が進んでいるホットスポットにも数えられている。
サバ州の森林面積は過去50年間に半減した。木材輸出の最盛時にはマレーシア1の経済を誇ったサバ州は、今ではマレーシア1の貧困層を抱えている。
自然保護というのはヨーロッパで20世紀に入って盛んになった思想、あるいは行政課題だが、その手法は、わずかに残った自然を囲い込み人間活動を排除し管理しながら保護するという方式であり、野生生物保護区、サンクチュアリーなどの管理方式が発展してきた。アメリカ、カナダ、オーストラリアなどの新世界もこの方式で国立公園や保護区を設置してきた。
欧米の植民地だった発展途上国は、こうした西洋風の自然保護行政を取り入れて来たが、社会文化の違いからうまくいってないところが多い。
特に東南アジアでは、伝統的な村落社会は自然資源に頼り生活を営んできたが、開発はそうした村落社会の外から持ち込まれ、資源にアクセスできる特権を持った人々(古くは占領国側、最近は都会の企業や資本家)のみが森林を伐採し、土地をプランテーション農園に開拓することにより富を得てきた。そして、開発に適応できない村落社会は保護区周辺に追いやられるという現象が起きてしまった。(自然と共生して生活してきた先住民は貧困層になるとの意)
日本は伝統的に自然との共生を大事にしてきた社会だった。明治時代の西洋化で自然破壊が一気に進み、西洋の自然保護思想も輸入されたが、基本的には自然との共生を基本的な価値観に自然保全行政が行われてきた。
欧米型と違い、国立公園や鳥獣保護区は人間活動を排除した囲い込みではなく、内部に住居、農業や観光業も内包した形で管理されてきた。
ボルネオに必要なのは、そういう日本型の自然保護方式を参考にしながら、東南アジア型の自然保全行政を構築することだと思う。
BBECのサイトを読むと、我々が何気なく使用している「自然保護」 の概念は欧米渡来の概念であり、アジアには必ずしも合致した概念ではない、との意味で印象的だったので、以下にBBECのサイトの一部を意訳抜粋してみた。
ボルネオ島の熱帯雨林は、地球上で最も生物多様性の高い地域であるが、その多様性の低下が進んでいるホットスポットにも数えられている。
サバ州の森林面積は過去50年間に半減した。木材輸出の最盛時にはマレーシア1の経済を誇ったサバ州は、今ではマレーシア1の貧困層を抱えている。
自然保護というのはヨーロッパで20世紀に入って盛んになった思想、あるいは行政課題だが、その手法は、わずかに残った自然を囲い込み人間活動を排除し管理しながら保護するという方式であり、野生生物保護区、サンクチュアリーなどの管理方式が発展してきた。アメリカ、カナダ、オーストラリアなどの新世界もこの方式で国立公園や保護区を設置してきた。
欧米の植民地だった発展途上国は、こうした西洋風の自然保護行政を取り入れて来たが、社会文化の違いからうまくいってないところが多い。
特に東南アジアでは、伝統的な村落社会は自然資源に頼り生活を営んできたが、開発はそうした村落社会の外から持ち込まれ、資源にアクセスできる特権を持った人々(古くは占領国側、最近は都会の企業や資本家)のみが森林を伐採し、土地をプランテーション農園に開拓することにより富を得てきた。そして、開発に適応できない村落社会は保護区周辺に追いやられるという現象が起きてしまった。(自然と共生して生活してきた先住民は貧困層になるとの意)
日本は伝統的に自然との共生を大事にしてきた社会だった。明治時代の西洋化で自然破壊が一気に進み、西洋の自然保護思想も輸入されたが、基本的には自然との共生を基本的な価値観に自然保全行政が行われてきた。
欧米型と違い、国立公園や鳥獣保護区は人間活動を排除した囲い込みではなく、内部に住居、農業や観光業も内包した形で管理されてきた。
ボルネオに必要なのは、そういう日本型の自然保護方式を参考にしながら、東南アジア型の自然保全行政を構築することだと思う。