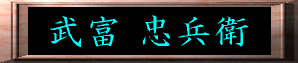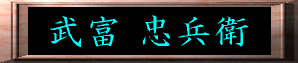武富忠兵衛は、佐賀藩家老“倉町鍋島家”の家臣(侍)である。
江戸時代初期の1637年(寛永14年)、肥前島原と肥後天草の農民が
天草四郎時貞を首領に奉じ、キリシタン信仰を旗印とした一揆を起こした。
いわゆる“島原の乱”である。
この島原の乱に際し、幕府は、九州の諸大名等に動員をかけ、
10数万の兵力で鎮圧に乗り出した。
この時、佐賀藩は、3万5千名ともいわれる大兵力を動員したのであるが、
その中に、この“武富忠兵衛”も、参加していたである。
忠兵衛は、一揆勢が篭城していた原城が落城のおり、相当に活躍したようで、
後に(元禄3年)、倉町鍋島家当主“鍋島一学”が佐賀藩庁に提出した戦功書に
その名が掲載されている。
原文 … 【 落城之節、相働候、 武冨忠兵衛 】
余談であるが、私の高祖も同名の“武富忠兵衛”である。
出生は、1800年頃であるので、
“島原の乱”鎮圧に際して活躍した“忠兵衛”とはだいぶ年代が異なる。
しかし、この当時、武士・百姓を問わず、名前というのは代々襲名されて
いくのが慣例のようになっていたのである。
また、倉町鍋島家と武富家は縁戚関係であるという事からも、
先祖の可能性が高いように思われる。
“島原の乱”鎮圧に活躍
※ 倉町家と武富家の関係については、“三保野”のページを参照下さい。