随想:幼少期へのタイムスリップ
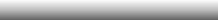
2.「のがわ」の源流を訪ねて(4)


春には桜並木となる「のがわ」
さて武蔵野雑木林を破壊した昭和40年代から20年間と言うと私が25歳〜45歳の時である。田中角栄の日本列島改造論で国中が沸いたのが昭和47年頃である。
このころは武蔵野に限らず、例えば全国の工業地帯がどんどん海岸に造成された時代である。鉄道、高速道路の計画も右肩上がりの経済を前提にして壮大なものが計画され実行に移されていた。
本四架橋で言えば神戸―鳴門ルートの大鳴門橋が竣工し、児島―坂出ルートの南北備讃瀬戸大橋が建設真最中の時期である。
この20年間私の会社の仕事も尋常の忙しさではなかった。毎日午前まで残るのは当たり前、土曜日も日曜日もなかった。
設計の現場でも、ある時は人間計算機、ある時は下請の手配師として日夜悪戦苦闘した。現場では人身事故も多かった。
右肩上がりで会社の業績を拡大させるためには都合の悪い事は報告をせず、されても握りつぶす風潮が自然に発生しても可笑しく無い状況だった。雪印も日本ハムも東電も三菱自工も風潮は似たようなものであったであろう。社会全体の風潮である。
この時期に関して私個人の生活で言えば、結婚したのが28歳、自家用車を手にしたのは30歳、最初に住宅を建設したのは33歳、次に引っ越したのは39歳である。
この日本全体が猛烈に突き進んだ甲斐あって、日本は高度成長を達成し経済的に豊かになった。どこかの国のように餓死者が数万人の事態は免れ、途上国に対する経済援助は鰻上りに上がっていった。個人で車を買って当然の時代になった。だが負の遺産も多かった。
一つが環境破壊である。その一例がこの広大な武蔵野雑木林と湿地帯の喪失である。またもう一つの大きな負の遺産がバブル崩壊により長く続く不況である。
「のがわ」源流を訪ねて自転車を漕いでいる間に、「のがわ」と私の会社生活40年間の出来事が複雑に交錯し頭が一杯になった。
11月には是非中央研究所の源流公開に参加したいと思う。但し参加者が多く列を作った上、一人何秒とかの見学会になるような気が私のこの1年間の東京生活の経験からは匂う。 (続く)
このころは武蔵野に限らず、例えば全国の工業地帯がどんどん海岸に造成された時代である。鉄道、高速道路の計画も右肩上がりの経済を前提にして壮大なものが計画され実行に移されていた。
本四架橋で言えば神戸―鳴門ルートの大鳴門橋が竣工し、児島―坂出ルートの南北備讃瀬戸大橋が建設真最中の時期である。
この20年間私の会社の仕事も尋常の忙しさではなかった。毎日午前まで残るのは当たり前、土曜日も日曜日もなかった。
設計の現場でも、ある時は人間計算機、ある時は下請の手配師として日夜悪戦苦闘した。現場では人身事故も多かった。
右肩上がりで会社の業績を拡大させるためには都合の悪い事は報告をせず、されても握りつぶす風潮が自然に発生しても可笑しく無い状況だった。雪印も日本ハムも東電も三菱自工も風潮は似たようなものであったであろう。社会全体の風潮である。
この時期に関して私個人の生活で言えば、結婚したのが28歳、自家用車を手にしたのは30歳、最初に住宅を建設したのは33歳、次に引っ越したのは39歳である。
この日本全体が猛烈に突き進んだ甲斐あって、日本は高度成長を達成し経済的に豊かになった。どこかの国のように餓死者が数万人の事態は免れ、途上国に対する経済援助は鰻上りに上がっていった。個人で車を買って当然の時代になった。だが負の遺産も多かった。
一つが環境破壊である。その一例がこの広大な武蔵野雑木林と湿地帯の喪失である。またもう一つの大きな負の遺産がバブル崩壊により長く続く不況である。
「のがわ」源流を訪ねて自転車を漕いでいる間に、「のがわ」と私の会社生活40年間の出来事が複雑に交錯し頭が一杯になった。
11月には是非中央研究所の源流公開に参加したいと思う。但し参加者が多く列を作った上、一人何秒とかの見学会になるような気が私のこの1年間の東京生活の経験からは匂う。 (続く)