| 特集 「バブル景気と廃墟について」 | ||||||||||||||||||
|
廃墟になるには理由がある。その一つとしてバブル景気というものがある。 今回は、廃墟と密接な関係があるバブル景気について少しだけ詳しくなって、今後の廃墟撮影の参考に なればと考えます。 ということで久々の特集企画「バブル景気と廃墟について」 |
||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||
|
バブル景気 1980年代後半、日本にはバブル景気という時代があった。 資産価格の上昇と好景気、及びそれに付随して起こった社会現象である。 実体経済から乖離(かいり)して資産価格が一時的に大幅に高騰し、その後急速に資産価格の下落が起こる様子が、中身のない泡がふくれてはじける様子に似て見えることから、「バブル景気」、「バブル経済」、また、その景気後退期を「バブル崩壊」などと呼称する。 |
||||||||||||||||||
|
大都市等の優良な土地の高騰にとどまらず、収益の見込めない遠隔地の土地もリゾート開発を名目に相当の値段で取引された。こうして得た土地を担保に、目に見えない現金の実態、数字だけの巨額の融資が行われ取引された。 土地の有効活用による収益ではなく、将来地価が上昇することで得られるだろうと見込まれる値上がり益を目的とすることが多かった。 土地を担保として融資を行うに際しては、通常は評価額の70%を目安に融資を行うが、将来の土地の値上がりを見越して過大に貸し付けることも珍しくなかった。破綻した北海道拓殖銀行では120%を融資した事例もある。単一の物件に複数の担保をつけることも行われた。 背景には、金融機関の貸出競争が激化する中、潤沢な資金をとにかく運用する、貸付に回す、という金融機関の姿勢もあった。 この融資の一部は後の地価下落(担保価値が低下)によって不良債権となった。 1987年リゾート法が制定され、都市から離れた地域においても、大企業を誘致してリゾート施設を開発する動きが活発となった。それまで見向きもされなかった土地が相当な価格で取引されるなど、土地価格の上昇に拍車をかけた。 1990年3月に大蔵省銀行局長土田正顕から通達された「土地関連融資の抑制について」(総量規制)に加えて、日銀による金融引き締めは完全に後手に回ったため急激なものとなり、信用収縮が一気に進んだ。信用崩壊のさなかにおいても金融引き締めは続けられ、経済状況を極度に悪化させた。前年に導入された消費税も経済実態に鑑みると導入が遅すぎたと言え、結果的に景気に悪影響を及ぼした遠因と考えられている。 |
||||||||||||||||||
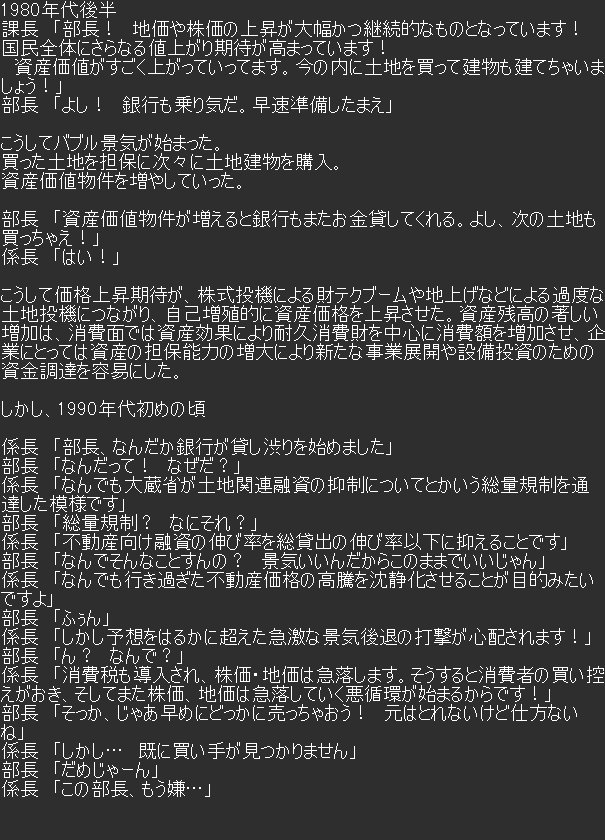
|
||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||

|
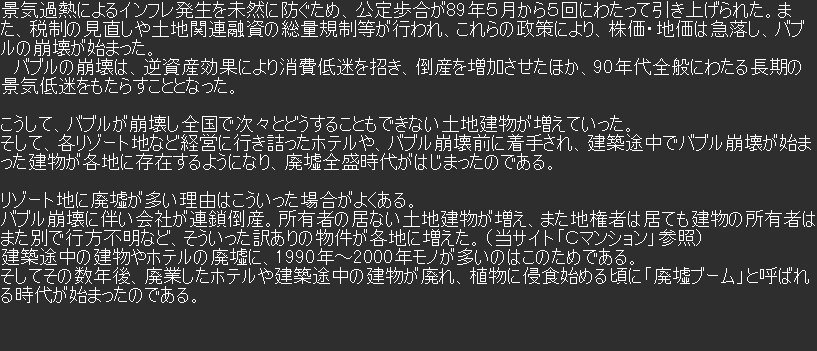
|
|||||||||||||||||
| 次の記事へ | ||||||||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||||||