

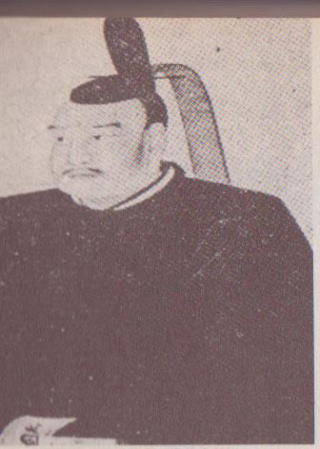
立花宗茂と
武士道
2016/1/11 更新
| 昔、韓国のソウルへ観光で行ったときの事ですが。バスガイドさんの話が、文禄、慶長の役の話になった時に、彼女の口から、 「加藤清正・立花宗茂・小西行長・島津義弘などが攻めてきた」といった。有名な大大名の中で、立花宗茂はまぎれもなく、我が 故郷の殿様でした。どんな人物か、朝鮮ではどんな戦いをしたのか?戦で一度も負けたことが無い。関が原の合戦で西軍であっ たのに、何故、再び大名に復帰できたか?地元では、ほとんど話題になってなかった。それから、興味が沸いてきました。調べれ ば調べるほど、すばらしい人物である事が判りました。自分が理想と思う人物は自分の故郷にいた。 何がすばらしいか? 武士道とは、立花宗茂の行ないそのものではないかと考えています。有名な「葉隠れ」は平和な時代のサラリーマン武士の 生き方のハウツーものとしての武士道であり実体が無く、鍋島藩の武士に武士としてのよき生き様を求めることは出来なかった。 本物の武士道とは、戦国時代の実践的な立花宗茂の生き様そのものです。 戦国時代の快男児、立花宗茂、 1.僅かな兵力で多くの兵力と戦い、勝つことが出来た。軍事的才能がある。 おおよそ2000人の軍勢で国内では秋月や島津、鍋島、京極と戦い、朝鮮では碧蹄館の戦いで明の大軍と戦い、蔚山城での 加藤清正の救出、露梁津での名将李舜臣との戦いに勝っている。彼は、「戦は兵数の多少ではない、一和にまとまった兵でなく ては、どれほど大人数でも勝利は得られない。」と言っていた。 2.自分の名誉への欲がないこと。私利私欲では動かない。 家康から50万石で誘いを受けても、秀吉への恩から大嫌いな石田三成や宇喜多秀家らの豊臣方に躊躇なく付いた。 3.高い評価や地位を得ても堕落しないこと。程をわきまえていて、自慢しない。 4.末端の兵や民への心配りが出来ること、えこひいきなどしない。ゴマすりを遠ざけた。ここが、他の権力者との決定的な違い です。 5.勇気があること。戦いでは勝つことに全力をあげる。驕り心や名誉を目的に戦わない。逆に戦は、油断したり、恐れたりする と負ける。 6.たとえ相手が誰であれ、へつらわない。 豊臣秀吉であれ、徳川家康であれゴマをすらない。 7.義理人情に厚いこと。仲間を大事にする。 8.憎い者でもダメな者でも、困ったときは命がけでも助けに行く。 佐々成政、加藤清正、小西行長の救援。 9.人を陥れるようなことをしない。 だまし討ちの誘いを受けても、卑怯な真似はしなかった。 歴史作家の海音寺潮五郎さんが、「最も尊敬する人物は、西郷隆盛と立花宗茂です。加藤清正や福島正則等は一応の価値は 認めるが尊敬する気にはなれない。」 最近、茅ヶ崎で立花宗茂の子孫の方とお会いしました。感激しました。 10月28日に行われた寒川合唱祭でも、立花宗茂の子孫の方にお会いしました。17代の叔父さんにあたる方で80歳でお元気です。 神奈川県藤沢市 小栁隆夫 |
|
| 項目 | 解説 |
| 父 高橋紹運 (吉弘) |
大友氏の武将であったが、秀吉の御家人として推挙され、秀吉の家人に加えられた。天正十四年北上
|
| 義父 立花道雪 (戸次鑑連) |
天正十二年(1584)、龍造寺隆信が肥前沖田畷の戦いで島津・有馬連合軍に討ち取られると、 立花道雪は龍造寺氏に占領されていた筑後の回復を目指した。豊後本国と共同作戦をとり、筑前 より出陣した道雪は、筑後山下城の蒲池鎮運等を降し、ついで要衝猫尾城を攻め落として黒木家 永を自害させた。しかし、柳河城の龍造寺家晴等の抵抗に手を焼き、豊後本国の軍勢の士気の低 さに戦意は思うように上がらなかった。やがて、長陣による疲労からか病を得て、天正十三年 (1585)九月十一日、享年七十三歳をもって御井郡北野の陣中で歿した。家臣は道雪の亡骸を守 って、立花城に帰還していった。道雪の死により、大友氏の筑後奪回作戦はついに空しくなった のである。道雪の死後、養子宗茂が家督を継ぎ立花城将となった。 |
| 妻 立花悶千代 |
宗茂の妻悶千代は美しく、教養もあり、武芸にも秀でた素晴らしい女性ですが、なぜか宗茂と息があい
|
| 弟 高橋統増 (立花直次) |
三池立花藩の藩祖となります、常に宗茂と共に戦いました。三池藩は、小さな藩ながらも江戸時代、
|
| 誕生 | 永禄10年(1567年)11月18日、豊後国(大分県)国東で大友家の重臣・高橋紹運の嫡男として 生まれる。幼名は千熊丸。初名は宗虎・統虎・鎮虎・正成・親成・尚政・政高・俊正・信正・ 経正など。永禄12年(1569)父に伴われ筑前岩屋城(太宰府)に移った。 |
| 幼小時代 | 宗茂が8歳の時、見世物があった。見物中、群集の中で喧嘩が始まり、ついには殺される者がで た。人々は慌てふためき逃げ散る中、宗茂は少しも恐れる様子もなく「今日の見世物はこれで終 わりか」と付き添いの者に尋ねた。早く逃げましょうという付き添いに対し宗茂は笑って「お前 たちが慌てるとはおかしな事だ。我々はあの喧嘩の相手ではないのだから、どうしてこちらに 切りかかってくることがあろうか。まだ見世物も終わっていないのに、ここから立ち去る必要も あるまい」といい、すべてを見終ってから帰ったという。 |
| 立花家の養子になる | 天正9年(1581年)、男児の無かった大友氏の重臣立花道雪は立花氏の跡継ぎとして高橋紹 運の子の高橋統虎(宗茂の初名)を養嗣子として迎えようとした。紹運は宗茂の優秀な器量と、 高橋氏の嫡男であるという理由から最初は拒絶しようとしたが、道雪が何度にもわたって請うて きたために拒絶できず、宗茂を道雪の養子として出している。このとき、宗茂は道雪の娘の立花 誾千代と結婚して娘婿となることで家督を継いだ。 |
| 少年時代 | 同じく少年時代、道雪の供と一緒に近くの山を散歩中、棘の付いた栗を足で踏み抜いた。当然の 如く、近習の者に「これを抜いてくれ」と頼むと由布惟信が駆けつけ、抜く所か逆に栗を足に押 し付けた、叫び声を上げようにも近くの駕籠の中からは養父の道雪が眉を吊上げて見ており、叫 ぶ事も出来ずに大変困ったと後年述懐したそうである。お坊ちゃま育ち故、立花氏に来てからは 大変厳しく教育されたそうである。 |
| 初陣 | 初陣天正12年7月、父とともに出陣、対秋月戦の嘉麻、穂波の戦いで初陣を飾る。その帰還の 途中の大友勢を秋月氏は追撃にでた。これにより石坂で両軍は接触、戦闘となった。この合戦で 宗茂は堀江備前と組み討ちし、押さえつけ、荻尾大学に首を打たせている。 |
| 立花城を守る | 天正12年 (1584年)8月、道雪・紹運の両将は大友氏の筑後奪回戦に参加するべく出陣。宗茂は 道雪出陣後の立花山城の留守を預かる事となった。この時、秋月種実率いる八千の兵が攻め寄せた が宗茂は夜襲でこれを撃破した。 |
| 岩屋城の戦い | この話は後日 |
| 立花城の攻防 |
|
| 柳川城主となる | 、秀吉の九州征伐に従って活躍、九州平定後の仕置によって筑後柳川に十三万二千石を与えら れて柳川城主となったのである。大友氏から独立した豊臣秀吉直臣大名にまで取り立てられた。こ のとき秀吉は、宗茂を「その忠義も武勇も九州随一である」「九州の逸物」(原文:その忠義、鎮 西一。その剛勇、また鎮西一。)と高く評価したという。 |
| 肥後一揆 | 天正15年(1587年)、佐々成政は移封後の肥後で、検地を行い、その為に国人が反抗し、大規模な国人一揆が発生した。平山城が孤立した時に、宗茂は平山城へ兵糧を輸送し、800の兵で1日に13度もの 戦いを行い、一揆方の城を7城も落とし、600の敵兵を討ち取るという武功を上げている。事前に、鍋島 勢が敗退した時の様子を調査し、敵が竹林に隠れて攻撃するのを予測していた。 宗茂は、この一揆の原因が佐々成政の悪政にあると感じ、隈部氏に対して同情的でした。そして、ひそ かに、隈部一族の一人を、名前を変えさせ家臣として残しました。また、この戦に参陣中に小早川隆景を 義父とし、小早川秀包とも義兄弟の契りを結びました。 また、悪政を行った佐々成政はこの責で切腹させられた。 |
| 立花統春 | 立花次郎兵衛統春は、立花道雪の甥にあたり、高義の人と知られ、高鳥居城攻めでは、星野吉美を打ち 取った武将です。肥後の一揆の後、佐々成政の後任に加藤清正が赴任してきた。加藤家内で紛争が 起き、罪人となった3人が立花統春をたよって逃げてきた。統春は彼らを匿ったが加藤清正が怒り、統春 の処分を要求してきた。若い宗茂は抗しきれず。統春に切腹を命じました。武士として恥じることはして ないと、統春は切腹をしました。 また、統春の妻と家人の11名も後を追って自害しました。若い宗茂にとって最も辛い出来事でした。 |
| タイ捨流剣術免許皆伝 |
タイ捨流剣術は新陰流上泉伊勢守信綱の門人丸目蔵人佐が興した剣術の流派で、戦場での戦いに有効な剣術で、宗茂は当時の柳川城主の蒲池鑑廣等とその門人となり、慶長元年、免許皆伝を受けました。合戦の戦術に大きな影響をうけています。 |
| 東の本多、西の立花 |
天正十八年(1590年)2月の小田原征伐にも従軍する。こののち、京で諸将が集まった場所で、秀吉が
|
| 四位に叙される |
秀吉から、四位の侍従(昇殿が許される。)に就任するとの内示があったが、前の当主の大友義統は、
|
| 朝鮮の役 |
文禄元年(1592年)、秀吉の朝鮮の役に、宗茂は、弟の高橋直次と共に三千の兵をひきいて参陣した。
|
| 錦山の戦い(8月18日) |
この話は後日 |
|
龍泉の戦い |
文禄元年(1592年)。明軍に追われて小西行長が平城から逃げ、旧主大友義統などが先を争って逃げる
|
|
碧蹄館の戦い(1月27日) |
ソウル郊外の碧蹄館で明と朝鮮の15万の大軍を迎撃し、大勝利した合戦の先陣をつとめた。鉄砲の
|
| 晋州城の攻撃(6月21-29日) |
第二次晋州城攻防戦では、明将劉綎が星州一帶に数万の明・朝鮮軍を集結させ、配下の琳虎に4万騎を
|
| 河東の戦い | この話は後日。 |
| 磐丹の戦い |
更に慶長の役の時、第一次蔚山城の戦いでは、明将高策率いる明軍5万は手薄になってた日本軍本陣の釜山を強襲する。宇喜多秀家は、驚き、宗茂に、その敵を討つよう命じた。宗茂はその夜は、大変寒い夜でしたが、8百の兵を率いて高策2万2千の兵に対し夜襲を行いこれを撃破、700の首を取った戦功を挙げ、史では磐丹の戦いを称えたという。
|
| 蔚山城の攻防 |
明将李如梅率いる明軍5万余騎が蔚山城を再度攻撃し(1598年5月4、5日)、守備に当たった加藤清正が
|
| 露梁津の海戦 |
島津軍の泗川倭城の大勝利から間もない10月8日。和議と撤兵を伝える使者として徳永寿昌、宮木豊盛が泗川倭城に到着しました。使者が伝えた内容によると、島津勢は泗川倭城を撤退して巨済島に移動し、順天倭城の小西勢と合流して釜山に帰る、という段取りになっていました。ところが、秀吉の死が水路軍総大将・陳リンの知るところとなると、状況が変わります。陳リンと朝鮮水軍の李舜臣は、順天倭城の小西勢の退路を断って殲滅する作戦に出ます。小西行長は撤退に際し、策謀家の 劉テイに多額の賄賂を贈って買収し、安全に撤退できるように軍を退かせることを約束させていました。ところが、順天倭城を船で出発してみると、退路には500隻もの連合軍の軍船が待ちかまえているわけではありませんか。驚いた小西勢は再び城に引き返すと、使者を出して劉テイに抗議しましたが、「自分は関与していない」とあっさり返答します。小西勢は退却することができずに敵に包囲されてしまったわけです。
|
| 関が原の合戦 |
慶長5年(1600年)、関ガ原の戦いでは、その直前に徳川家康から五十万石という法外な恩賞を約束に
|
| 大津城の城攻め |
その後、豊臣方の勝利を確信した宇喜多秀家は、9月7日、西軍の最強部隊の立花宗茂と毛利元康、
|
| 瀬田の唐橋 |
逃げる西軍が、瀬田の唐橋を焼き落とそうとしていたのを、「庶民が難儀するから」と止めさせた。後に伝 |
|
大坂城篭城戦を主張 |
大坂城に退いた後、宗茂は、大坂城に籠もって徹底抗戦しようと総大将の毛利輝元に進言したが、 |
| 島津義弘 |
九州に引き上げる途中、瀬戸内海周防国屋代島の日向泊で関ヶ原の戦いに敗れ敵中突破して来た島津
|
| 江上八院の合戦 |
しかし、国元に帰った宗茂に対して、西軍であった鍋島勝茂、さらに東軍で秀吉子飼いの加藤清正、黒田如水らが出陣してきた。このとき、鍋島勢は西軍に加担したことを挽回しようとして懸命であったのに対して、加藤・黒田氏らは宗茂を攻めることには消極的であったという。宗茂は家康への恭順を示すため城に残り、家臣団だけで出陣した。家老の小野鎮幸を総大将とし、一千三百余人の兵を率いて、鍋島三万二千の大軍と対峙し、江上八院の戦で一度は勝利を収める。後に本城である柳川城に篭城し、加藤清正の説得を受けて降伏・開城することとなる。また、島津義弘は国許へ帰ると、宗茂から受けた恩義に報いるために柳川へ一万の援軍を送った。しかし、援軍が柳川へ到着したのは開城から三日が過ぎた後だったという。島津から、種子島一島をやるから、薩摩へ来ないかと云って来た。しかし、宗茂は断りました。
|
| 改易される | しかし、島津家は本領安堵されましたが、立花家は改易され、宗茂は浪人となります。その器量を惜しんで 加藤清正や前田利長から家臣となるように誘われるが、宗茂はこれを拒絶した。そこで清正は、家臣にす ることを諦め、食客として遇したという。 |
| 江戸へ |
その後、加藤清正のもとを去る決心をした宗茂は、慶長七年、江戸に上る旅に出ました。その時宗茂
|
| 御書院番に任ぜられる | 翌八年、本多忠勝の推挙で宗茂は江戸城に召し出され、秀忠から御書院番(将軍の親衛隊長)として五千 石を給されることになった。50万石での誘いを断り、大津城の攻略と江上八院の合戦で二度も徳川家康 に弓を引いた宗茂が、三河以来の者よりも信頼されました。この間、宗茂は徳川家に媚びたり、へつらっ たり猟官運動をすることはまったくなかった。 かくして、幕府の要人に迎えられた宗茂は、以後、徳川家 に忠勤を励みました。 |
| 大名に復帰する |
まもなく陸奥国棚倉(福島県棚倉町)に1万石を与えられて大名として復帰した。翌年には同地で
|
| 新井の橋 |
幕閣が新井に橋を作った事を怒った二代将軍徳川秀忠に「徳川家の治世がよく、戦の無い世に
|
| 大阪夏の陣 |
大坂の陣のとき、家康は宗茂が豊臣方に味方するのを恐れて、その説得に懸命に当たったという、そして
|
| 柳川へ復帰する | そして、それら徳川家に対する忠勤が認められ、元和6年(1620年)、幕府から旧領の筑後国|筑後柳河藩 に10万9,200石を与えられ、大名として完全に復帰を果たした。関が原の合戦から20年後のことでした。 同時に弟の直次の子も筑後三池藩1万石の大名に復帰しました。東軍西軍に関わらず、些細なことで、 数多くの大名が取り潰される時代に、西軍の武将で徹底的に東軍と対峙したのに、元の領地に復活した のは奇跡でありました。まことにめでたい運に恵まれた宗茂であったが、生来の信義と愚直さと器の大き さが、秀吉・家康らの覇者に愛されたのであろうと思います。そして、柳川へ船で帰還した宗茂一行を大勢 の 庄屋、百姓、旧家臣が、涙を流しながら迎えました。 |
| 相伴衆となる | また、戦国武将としては世代が若く、伊達政宗や加藤嘉明、丹羽長重らとともに、秀忠から将軍職を譲り 受けた徳川家光に戦国の物語を語る相伴衆としての役目も果たした。 徳川幕府が開かれたとはいえ、世の中はまだ混沌としており、幕府=徳川家にしてみれば、新しい 支配体制を作り上げることは急務であった。そのようなおり、宗茂の誠実で信頼できる人柄と、かくかく たる戦歴は幕府=徳川家に得がたいものであったと思われる。 |
| 旧臣を登用 | 柳川へ復帰した宗茂は、取り潰された前筑後柳川藩主田中吉政の家臣を一人も登用せず、加藤家や 黒田家に使えていたり、柳川に残っていた旧臣を集めて登用した。そもそも、親友の石田三成を 捕えた手柄で、大大名になった吉政が嫌いであった。 |
| 城の改築をせず | 城の改築について、宗茂は、「立派な屋敷だと下々のものが寄りつかなるし、上と下との差が 大きくなる。ボロ屋敷でも家の名には傷が付かない。田中吉政は、立派な家屋敷を持った、その 為に財政が逼迫し、大阪夏の陣に参軍出来ず、ついには滅んでしまった。」  |
| 黒田藩をかばう | 黒田騒動に際して、幕府に「黒田藩には何事も起こっていない」と報告し、黒田家の窮地を救った。しかし、 激しい内紛の熊本騒動では、立派な熊本城を建てた加藤家の取り潰しを防ぐ事は出来なかった。 |
| 誾千代を弔う |
正室の誾千代を弔うために、山門郡瀬高上荘の来迎寺の住職で、かつての柳川城主の蒲池鑑盛(
|
| 島原の乱 | 寛永14年(1637年)には島原の乱にも参陣した。江戸に居たが、徳川家光より,水野勝成と共に派遣され た。両者とも70を超えていたが、信長・秀吉の時代から何十という戦場で勝ち抜いて来ただけに、ついに、 出番がきたと思われる。二月六日に着陣し、松平信綱に持久戦を進言した。戦略面の指揮を行い、原城 攻城時には昔日の勇姿を見せた。諸大名は武神再来と嘆賞した。 |
| 小功を言い立てず |
原城の攻防時に、城への一番乗りを果たした三池立花藩兵が、一番乗りの手柄を細川藩兵に取られて争いになった時に、「一揆との争いで手柄争いはするな」と、窘めました。 |
| 松平信綱をかばう |
島原の乱の幕府の総指揮者の松平信綱の不評を、将軍家光に「若年ながら、事ごとに痒い所に手
|
| 太閤記の小瀬甫庵 |
太閤記の小瀬甫庵が、「貴殿の記録を話して下さい」と求めました。宗茂は、笑って「私のしたことは天下の公論
|
| お墓 |
七十六歳で江戸藩邸で胃がんで死去。練馬桜台の広徳寺に墓があります。しかし、柳川本町の福厳寺に改葬され、今は墓石だけが残っています。戒名は、大円院殿松蔭宗茂大居士
|
|
|
|
| 文献 |
1)名将言行録(中) 岡谷繁実原著 ニュートンプレス |
立花宗茂
ただいま工事中です。しばらく、お待ちください。