ウォンディ・ポダンより眺めた段々畑
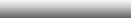
写真−59

ウォンディ・ポダン


2004年4月1日
経済的なことなど ‥‥
ブータンの政治、経済のことは観光案内書に記載されている程度のことしか分からない。基本的には農業主体の自給自足経済と言う。従って農民は税金を納める必要はない。豊かな農村の民家には2〜3年分の米が蓄えられ、見栄を張って来客があると米で手を洗うとも聞いた。先にも書いたが学校は無料、医療費も無料である。
かつて海外技術協力事業団の西岡さんがブータンの風土にあった農業の近代化を指導して豊かな国になったとも聞いた。西岡さんはブータンに住み付きブータンで亡くなったが、葬儀は国葬で300人の僧侶が読経したとのこと。西岡さんのお蔭で日本人はブータン人から尊敬を受けているらしい。
現国王が外交に巧みで、国の経済のかなりの部分をODA(政府開発援助)に頼っているとも聞いた。他国では政府高官がODAの上前をはねてしまい末端に行き渡るのは一部しかない場合があるそうだが、ブータンではそのような汚職や賄賂はない。数字的なことは分からないが国土が狭く人口が少ないブータンではODAの絶対額は少なくても一人当たりにすれば大きいのだと思う。
街を歩いたり山間部をバスで走っている時に気が付いたが、建築工事や土木工事はインドやネパール系の人たちが行っている。彼らはにこやかなブータン人に比べて厳しい顔つきをしている。住居もはるかに貧しいトタン小屋のようだった。移民とのことだがこの辺りの事情はよく分からない。
華やかなツェチュ祭も参加はブータン人だけであり、インドやネパール系の人は祭の日でも土木作業をしていた。彼らは別のお祭をするらしい。
ブータンは平地が少ない(殆どない)土地柄だが厳しい傾斜地に段々畑(棚田)を営々と築いているのを見ると、ブータン人は農作業は好きで勤勉な民族と思われる。ヒマラヤ山脈からの小河川が多く、それほど無理なく棚田が成り立っているのだろう。小河川が荒れ狂う大河になるのは南方のインドやバングラデシュに到達してからである。
砂漠の強権政治下の潅漑地帯では水の利権に腐敗政治が群がり農民が犠牲になっている国もあるが、ブータンではそのような図式はなく共同体としての「ムラ」が有効に機能しているように見えた。
畑は稲作主体で野菜はトマト、ナス、瓜、ジャガイモ、ほうれん草、アスパラ、カリフラワーなど日本と同じものが多い。
電力はインドの金でブータンに水力発電所を作り、ブータンがインドに電力を輸出しているとのこと。従ってブータンでは電力は余っているのだが設備のメンテナンスが悪いためかホテルでも短時間の停電が何度もあった。携帯電話も普及し始めている。これもODAによるものである。
ブータンも近代化に伴い自然還元できないゴミが増えており、その回収システムが無いためゴミが目立つ。ツェチュ祭の広場の周囲でも最終日にはかなりのゴミがばら撒かれていた。
観光客の残すゴミも多い。タクツァン僧院への登山道にも菓子の包み紙などのゴミがあったが、参加した旅行社の添乗員は大きなビニール袋を用意して下山時にゴミを回収していた。ブータン人が感心していた。
かつて海外技術協力事業団の西岡さんがブータンの風土にあった農業の近代化を指導して豊かな国になったとも聞いた。西岡さんはブータンに住み付きブータンで亡くなったが、葬儀は国葬で300人の僧侶が読経したとのこと。西岡さんのお蔭で日本人はブータン人から尊敬を受けているらしい。
現国王が外交に巧みで、国の経済のかなりの部分をODA(政府開発援助)に頼っているとも聞いた。他国では政府高官がODAの上前をはねてしまい末端に行き渡るのは一部しかない場合があるそうだが、ブータンではそのような汚職や賄賂はない。数字的なことは分からないが国土が狭く人口が少ないブータンではODAの絶対額は少なくても一人当たりにすれば大きいのだと思う。
街を歩いたり山間部をバスで走っている時に気が付いたが、建築工事や土木工事はインドやネパール系の人たちが行っている。彼らはにこやかなブータン人に比べて厳しい顔つきをしている。住居もはるかに貧しいトタン小屋のようだった。移民とのことだがこの辺りの事情はよく分からない。
華やかなツェチュ祭も参加はブータン人だけであり、インドやネパール系の人は祭の日でも土木作業をしていた。彼らは別のお祭をするらしい。
ブータンは平地が少ない(殆どない)土地柄だが厳しい傾斜地に段々畑(棚田)を営々と築いているのを見ると、ブータン人は農作業は好きで勤勉な民族と思われる。ヒマラヤ山脈からの小河川が多く、それほど無理なく棚田が成り立っているのだろう。小河川が荒れ狂う大河になるのは南方のインドやバングラデシュに到達してからである。
砂漠の強権政治下の潅漑地帯では水の利権に腐敗政治が群がり農民が犠牲になっている国もあるが、ブータンではそのような図式はなく共同体としての「ムラ」が有効に機能しているように見えた。
畑は稲作主体で野菜はトマト、ナス、瓜、ジャガイモ、ほうれん草、アスパラ、カリフラワーなど日本と同じものが多い。
電力はインドの金でブータンに水力発電所を作り、ブータンがインドに電力を輸出しているとのこと。従ってブータンでは電力は余っているのだが設備のメンテナンスが悪いためかホテルでも短時間の停電が何度もあった。携帯電話も普及し始めている。これもODAによるものである。
ブータンも近代化に伴い自然還元できないゴミが増えており、その回収システムが無いためゴミが目立つ。ツェチュ祭の広場の周囲でも最終日にはかなりのゴミがばら撒かれていた。
観光客の残すゴミも多い。タクツァン僧院への登山道にも菓子の包み紙などのゴミがあったが、参加した旅行社の添乗員は大きなビニール袋を用意して下山時にゴミを回収していた。ブータン人が感心していた。